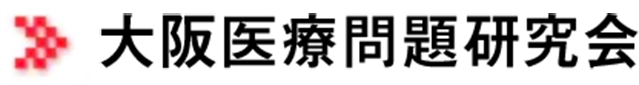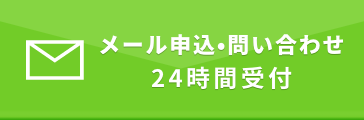救急搬送有料化のメリット・デメリット
2025.08.30
現在、救急搬送は原則として無料で行われているところ、そのために軽症患者によるいわゆる「タクシー代わり」の利用や、夜間・休日の安易な要請が増加しており、救急隊や救急病院に大きな負担がかかっていることが社会問題として取り上げられていることはご承知の方も多いかと思います。こうした不適正利用を抑えるための方策として、有料化の導入が検討され,実際に一部の自治体や病院で有料化する動きが広がってきています。救急車の有料化をめぐる議論は、日本における救急医療体制の持続可能性をどう確保するかという大きな問題に直結しています。
有料化のメリットとしては、まず第一に、不必要な利用を抑制できる点が挙げられます。軽症患者が自己負担を意識すれば、救急車を呼ぶ際に「本当に必要か」を考えるようになり、結果として本当に救急対応が必要な重症患者の搬送が迅速に行えることにつながります。第二に、救急隊や病院の業務負担の軽減につながり、限られた医療資源を効率的に活用できる点も大きなメリットの一つです。第三に、救急搬送にかかる莫大な費用の一部を利用者に負担してもらうことで、自治体の財政負担を軽減する効果も期待できます。さらに、医療機関の救急外来への軽症患者の集中を緩和し、救急医療全体の効率化につながる可能性もあります。
しかしながら、デメリットも重大です。最大の問題は、利用者が費用を気にして救急要請をためらうことで、命に関わる重症患者の搬送が遅れるリスクです。市民の方々が自分で症状の軽重を正確に判断することは難しく、本来搬送が必要なケースでも「お金がかかるなら」と思い控えてしまえば、結果として重症化や命にかかわる事態に陥るリスクがあります。これは、かえって医療費や介護費が増える事態につながるおそれもあります。また、料金徴収や所得による免除制度の設計、運営コストも無視できず、むしろ新たな行政コストを生むおそれもあります。
結局のところ、救急車の有料化は、医療資源の効率的運用や財政負担軽減といった合理性を持ちながらも、生命の安全保障という救急制度の根本的使命との間で難しいバランスを迫られる問題です。全国一律全額有料化は現実的ではない一方で、軽症者に限った部分的有料化や、悪質な利用に対するペナルティ導入など、限定的な形での活用が現実的な妥協策として検討されています。重要なのは、有料化そのものを目的化するのではなく、「真に必要な人が迅速に救急医療を受けられる体制をいかに維持するか」という観点から、総合的な制度設計を慎重に議論していくことだと考えます。
なお,救急車を呼ぶべきかどうか迷ったときは,「#7119」(救急安心センター事業)に電話で相談する窓口もあります。看護師などの専門家が症状を聞き取り,救急車の必要性や医療機関の受診についてアドバイスをしてくれる体制もありますので,迷ったときは一度ご相談されることをご検討ください。
会員弁護士 M.M