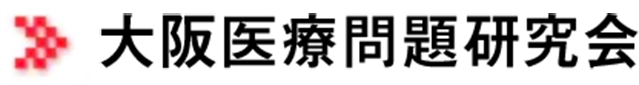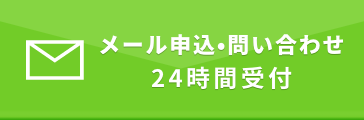はい。どんな診療科目でも相談に応じることができます。
但し、弁護士は医師ではありませんので、相談の時点で全てのご質問に回答することはできません。
事案について弁護士は患者側に協力してくれる各診療科目の医師(協力医)のアドバイスを得て回答することもあります。
協力医の協力を得る場合、医師に対する費用も発生します。したがって、相談に対する専門的な回答には、時間と費用が必要となります。
(費用の詳細についてはQ30へ)

相談にあたって
相談の内容・可否について
Q1 どんな診療科目の相談にも、応じてもらえますか?
Q2 相談申込みをすれば、必ず相談に応じてもらえるのですか?
相談申込みをされても、それが法律上の問題ではなく、医学上の問題だけである場合、刑事事件のみに関する相談の場合には、原則として相談に応じられません。
Q3 治療のための医療機関の紹介や治療方法のアドバイスはしてもらえますか?
いいえ。医療機関の紹介や治療方法のアドバイスは、法律問題ではありませんので、相談には応じられません。
Q4 私は大阪府外に居住していますが、相談に応じてもらえますか?
はい。相談に応じます。但し、当研究会に所属する弁護士の法律事務所は大阪府内にあります。
相談される方は、原則として、その弁護士の法律事務所まで出向いていただくことになります。
Q5 相手方の医療機関が大阪府外にありますが、相談に応じてもらえますか?
はい。相談に応じます。
但し、相談後に交渉・訴訟などの法的手続を委任された場合、相手方医療機関が大阪府から遠く離れた場所にあるときは、交通費・日当などの実費が特別に発生することもあります。
くわしくは、担当弁護士に費用についてお尋ねください。
(費用の詳細についてはQ30へ)
相談の方法・準備について
Q6 相談申込をした後、担当弁護士から連絡が来るまで、何日くらいかかりますか?
原則として、申込をした日の翌日から二営業日までに連絡いたします。
Q7 相談は、被害を受けた患者本人がする必要がありますか?
いいえ。相談だけでしたら、患者本人でなくても相談に応じることができます。
しかし、交渉・訴訟などの法的手続をとる場合は、患者本人から直接事情を伺い、その意思を確認する必要があります。
また、患者本人の意識がないなどの特別の事情があるときは、成年後見などの手続をとる必要がある場合もあります。
Q8 弁護士に相談をしたことが、医療機関側や第三者に伝わりますか?
いいえ。弁護士は相談を受けた内容について守秘義務を負っていますので、医療機関側や第三者に相談したことが知られることはありません。
Q9 メールや電話での相談はできますか?
いいえ。医療過誤に関する相談にあたっては、詳細な事情の聴き取りや複雑な法律上の説明が必要となるため、メールや電話での相談では誤解を生じるおそれがあります。
そのため、メールや電話での相談は、行っておりません。
Q10 相談にあたって、どのような準備をしていけばいいですか?
相談を円滑に行うため、病気の発症・治療経過・医療機関とのやりとりなどの出来事を、日時順に記載したメモを事前に作成することをお勧めします。
既にカルテや検査記録などの医療記録がお手元にある場合は、それを持参したほうが良いかどうか、担当弁護士にご相談下さい。
Q11 相談の前に、あらかじめ医療記録等を取り寄せる必要はありますか?
事前に取り寄せる必要はありません。医療記録等の入手については、担当弁護士にご相談下さい。(医療記録の入手の詳細はQ21へ)
相談料について
Q12 相談料はいくらかかりますか?
法律相談は有料です。料金は相談担当弁護士に直接ご確認ください。
相談を担当する弁護士について
Q13 どのような弁護士が相談を担当していますか。
本研究会の医療過誤事件の経験のある、弁護士が必ず担当します。
Q14 担当弁護士を指名したり、担当弁護士の条件を指定することはできますか?
いいえ。担当の弁護士を具体的に指名することはできません。
また、例えば、「被害を受けた診療科に詳しい弁護士を紹介してほしい」「ホームページに掲載された事例を解決した弁護士を紹介してほしい」などといった担当弁護士の条件も指定することはできません。
相談後の対応について
Q15 医療機関に対して損害賠償請求等を行う場合には、弁護士に依頼した方がよいでしょうか?
医療過誤事件の交渉・訴訟は、貸金請求訴訟などの一般的な民事事件に比べ、医学的にも法律的にも高度の専門知識を必要とすることが多く、難しい事件であることがほとんどです。
したがって,医療機関に対する損害賠償請求などの交渉や訴訟をお考えの方は,まず,医療過誤事件を多く扱う弁護士に相談することをお勧めします。
Q16 相談担当弁護士は、お願いすれば、医療機関との交渉や訴訟を必ず受任してくれるのでしょうか?
相談担当弁護士が必ず受任するとは限りません。
医療機関に対し交渉や訴訟をしても、損害賠償を受けられる見通しがない場合や相談者と担当弁護士との間で信頼関係が築けない場合は、受任をお断りすることもあります。
Q17 相談担当弁護士の回答に納得できなかったり、相談担当弁護士に受任してもらえなかったりした場合、再度、弁護士を紹介してもらえますか?
いいえ。弁護士の紹介は、原則として一回に限っています。
相談後の流れ
医療過誤事件の解決方法について
Q18 弁護士に依頼した場合,すぐに訴訟をするのですか?
いいえ。すぐに訴訟することはありません。
依頼を受けると、まず,医療記録および医学文献などの資料を入手し,「医療機関に対して法律上の責任を追及できるか」という観点から、協力医の意見を聞きながら、調査を行います。
医療過誤事件においては、訴訟などの法的手続になると、弁護士費用・鑑定費用など相当の費用が発生することが多くなります。したがって、医療機関に法律上の責任を問えるのか、事前調査により事件の解決の見通しを立てることが非常に重要です。
このため、医療過誤事件では、医療機関の過失の有無について見通しを立てる事前調査のみを受任する場合も少なくありません。
Q19 事前調査後は、どのような流れになりますか?
担当弁護士は調査結果を報告し、医療機関に対する法律上の責任追及ができる可能性があるかどうかの見通しを説明します。
その後、担当弁護士は依頼者と相談の上、医療機関に対する損害賠償請求の交渉・訴訟などの法的手続を新たに受任します。
事前調査の結果によっては、この時点で医療機関に対する責任追及を断念することもあります。
Q20 解決のための法的手続には、どういうものがありますか?
事件の解決に向けて、次のような方法があります。
1.交渉
医療機関との間で、直接、損害賠償請求の話し合いを行います。医療機関が話し合いによる解決に応じれば、この段階で示談が成立し、事件が解決することがあります。
2.調停・ADR(あっせん)
患者側および医療機関との間に、中立の第三者をおいて、相手方と話し合いをする手続です。
裁判所に申立てを行い、裁判官や調停委員の仲立ちで話し合いをする調停手続や、民間の第三者機関の仲立ちで話し合いをするADRなどがあります。
これらの方法は訴訟に比べて、早期に、簡単な手続での解決が期待できますが、相手方が調停・ADRに応じてくれることが条件になります。
3.訴訟手続
裁判所に訴訟を提起して進める裁判手続です。 (それぞれの方法の長所・短所についてはQ27へ)
医療記録などの資料収集の方法
Q21 カルテなどの医療記録は、どのように集めれば良いのでしょうか?
①医療機関から直接、医療記録のコピーを入手する方法と、
②裁判所に「証拠保全」の手続を申し立て、裁判所を通じて入手する方法があります。
Q22 どのようにして、医療機関から直接、医療記録を入手するのですか?
患者には,個人情報保護法に基づいて、医療機関に対して医療記録の開示請求をする権利があります(但し、コピーの費用は患者負担となります)。
具体的には、患者本人が医療機関の事務手続担当者に医療記録のコピーを請求したいと伝え、医療機関所定の申請書を提出することが一般です。なお、個人情報保護法に基づく医療記録の開示請求を患者から依頼を受けた弁護士が行うこともあります。
個人情報保護法に基づいて医療記録を入手する方法は、簡易な手続であり、証拠保全に比べて費用がかからないという利点があります。他方,医療機関が医療記録の改ざん・廃棄する危険性は「証拠保全」の手続に比べて大きいとされています。
Q23 「証拠保全」とはどのような手続ですか?
裁判所に対し「証拠保全」の申立を行い、申立が認められると、裁判所が医療機関に赴き、医療機関において患者の医療記録の有無・状態を直接確認して、証拠を保全する手続です。通常、裁判所はその場で医療記録のコピーを持ち帰ります。
裁判所は「証拠保全」を行うことを、直前まで医療機関には知らせずに手続を進めるため、医療記録の改ざん・廃棄を防ぐことができます。また、場合によっては、カルテ以外の患者に関する記録を収集することも可能であり、優れた資料収集の方法です。
しかし、証拠保全手続は、裁判所への申立を行い、審理を経る必要があり、弁護士費用やその他実費などの特別の費用がかかります。(費用の詳細についてはQ30へ)
弁護士費用・法テラス利用などについて
相談の結果、事実の調査や訴訟手続を行うことになりましたら、弁護士との間で委任契約を締結します。その委任契約の中で、弁護士費用を決めることになります。
Q24 法テラスは利用できますか?
法テラスの制度については弁護士の間で様々な評価がありますので、法テラスを利用できるかどうかは、担当弁護士の方針により異なります。法テラスを利用できるかどうかは、担当弁護士にご確認ください。
Q25 完全成功報酬制の委任契約はできますか?
多くの委任契約では、弁護士費用として、着手時に着手金を、委任事務終了時に成功報酬をそれぞれ支払うという内容になっています。一方、完全成功報酬制とは、着手時の着手金を支払わず、訴訟等で目的を達した時に初めて弁護士費用全額を支払うという内容の契約です。このような委任契約については弁護士会内に否定的な評価もありますので、完全成功報酬制の委任契約はできないと考えてください。
Q26 弁護士に依頼する場合,弁護士費用はどのくらいかかりますか?
弁護士に対してどのような手続を依頼するか,損害賠償額をいくら請求するかによって,弁護士費用は異なります。
具体的な金額は,担当弁護士が所属する法律事務所の報酬規程によって決まりますので,詳しくは,担当弁護士にお尋ねください。
Q27 弁護士費用のほかに,必要な費用はありますか?
実費として,医療記録などのコピー代・交通費・切手代・裁判所に納める印紙代・鑑定費用、遠方出張に伴う弁護士の日当などを要することがあります。
実費の額は,事件によって異なります。事件を依頼する前には,担当弁護士から,十分な説明を受けていただくようお願いいたします。
訴訟について
Q28 訴訟はいつでも起こすことができますか?
時効で請求権が消滅しない限り,いつでも損害賠償請求訴訟を提起することが可能です。
医療機関に対する請求権は,通常は,問題となる医療行為のときから10年で消滅時効にかかります。
医療機関に勤務する医師個人に対する損害賠償請求権は,3年の消滅時効にかかります。
時効の起算点をどのように考えるかによって,消滅時効の期間が経過しても提訴が可能な場合があります。しかし,医療行為から時間が経てば経つほど,証拠となる資料の収集が困難になるので,できる限り早期に訴訟を提起することが望ましいです。
また,医療記録の法定の保存期間は記録によって異なり、2年から最長5年となっていますので,その点にも注意が必要です
Q29 訴訟を起こした場合、どのような進行になりますか?
原告(患者側)が訴状を裁判所に提出し,訴状を受け取った被告(医療機関側)は,反論をまとめた答弁書を裁判所に提出します。
その後は,医療機関の過失や、患者の被害(損害)との因果関係など事件の争点について、原告・被告双方が主張書面を提出し,その主張の根拠となる医学文献や医師の意見書等を提出します。
さらに、原告・被告双方から裁判所に提出された証拠だけでは過失や因果関係が不明だと考えられる場合には,裁判所が選任する第三者の医師による鑑定や医師の専門委員に意見を求める手続が実施されることもあります。
また、原告本人や治療を担当した医師などの尋問が行われることもあります。
これらの審理を経て、裁判所は医療機関側の法的責任の有無を判断して判決を下します。
なお、裁判所は、訴訟の進行に応じて原告・被告双方に和解案を提示し、双方が納得すれば、和解が成立して事件が解決することもあります。
Q30 訴訟による事件の解決までにはどれぐらいの期間がかかりますか?
医療訴訟は,貸金請求訴訟など他の一般民事事件に比べてはるかに時間がかかります。
通常の民事事件全体の平均審理期間(判決又は和解により事件が終結するまでの期間)は,10ヶ月程度であるのに対し,医療訴訟の平均審理期間は,2年以上と言われています。仮に,第1審の判決に対して控訴があった場合は,より長期となります。
Q31 訴訟以外の手続きによる解決と訴訟による解決手段ではどのような違いがありますか?
訴訟以外の手続には,簡易裁判所での調停,裁判外での紛争解決手段であるADRなどがあります。
いずれも話し合いによる解決に主眼が置かれており,例えば、医療機関の過失が明らかであるが,損害額に争いがあるといった事案,医療機関側に治療経過などの説明を求めたいといった事案などにおいて,利用することが考えられます。
患者と医療機関の間で、損害額のみが争われている事案であれば、解決までにの時間はそれほどかからないことが多いと言えます。
しかし,過失や因果関係の有無が争われる事案は,話し合いによる解決が難しいため、時間はかかりますが、最終的に裁判所が判決を下す訴訟の方が、解決手段として適しているといえます。
Q32 医療訴訟は難しい訴訟といわれてますが、患者側が勝訴することは難しいのでしょうか?
患者側の勝訴率は決して高くはありません。
大阪地方裁判所には医療事件の専門部がありますが,専門部の判決において患者側の勝訴率は10%以下と言われています。
ただし,和解で終了する事件も多くあり,和解による解決事案には、患者側の請求がほぼ認めらるような勝訴的な和解が行われている事案も相当数あると思われます。
患者側が勝訴するために,患者側弁護士は多くの医療文献や医師の意見書等を十分に準備して,医療機関側の過失及びその当該過失と結果との因果関係を立証しなければなりません。
たとえば、単に治療の結果が悪かったから過失があるに違いないといった主張だけでは,医療機関別の過失を証明することは困難です。
従って、患者側が勝訴する見込みがどの程度あるか、訴訟をする前の見極めが重要となります。