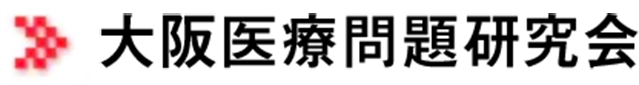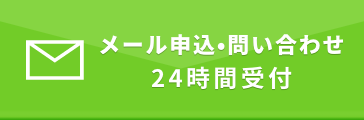医療事故訴訟における証明度に関する論考-6:4の蓋然性説
2025.07.30
以前のブログ記事で、医療事故訴訟における証明責任の基準について、高度の蓋然性ではなく相当程度の蓋然性として6:4程度の差があれば当該事実を認定すべきとする元裁判官の須藤典明氏の文献(「民事裁判における原則的証明度としての相当程度の蓋然性」民事手続の現代的使命-伊藤眞先生古稀祝賀論文集)有斐閣342頁)をご紹介しました。
https://osakairyo-ken.net/blog/catgory01/192/
須藤氏が新たに執筆された文献で、このテーマを更に深く掘り下げて検討されていますので、その内容を簡単に紹介いたします(「医療事故訴訟における証明責任と証明度」最新裁判実務大系第13巻 損害賠償訴訟Ⅱ -医療・国家賠償・地方自治-161頁)。
以前の文献では、須藤氏は「相当程度の蓋然性」という用語を用いていましたが、それは誤解を招きやすいとして「6:4の蓋然性」という用語に改めています。用語の名称自体は変更されていますが内容は同じです。すなわち、証明度の基準として、高度の蓋然性ではなく、6:4の蓋然性を基準とすべきというものです。
須藤氏の見解によれば、立証に6:4程度以上の明らかな優劣差があれば、裁判官はもとよりほとんどの弁護士もその違いを認識することが可能であり、その事実を訴訟上の事実と認定することはより真実に近い事実を認定することができる、というものです。
特に強調されているのが、誤判には、①認定した事実が真実ではないという「積極的誤判」と、②真実であったのに認定されなかったという「消極的誤判」があるところ、証明度を高めるほど消極的誤判が増えて、全体としての誤判率が高まる、という点です。つまり、高度の蓋然性を用いて証明度を高めることは、結果として誤判が増えてしまうことになります。
6:4の蓋然性を採用する場合、高度の蓋然性に比べて十分な審理がされないイメージをもたれることがありますが、須藤氏は、それは誤解として明確に否定します。すなわち、証明度が事実認定の基準として機能するのは、訴訟が裁判をするのに熟したとして結審された後のことであるから、解明度や審理充実度とは直接の関係はない、ということです。高度の蓋然性・6:4の蓋然性いずれを採用する場合でも、当事者双方が自身の主張する事実が正しいことを裁判官に理解してもらうために精力的に主張立証して充実した審理が行われることを前提として、そのような審理がされた後の事実認定のレベルでどの証明度を採用するか、という問題になります。6:4の蓋然性を採用したからといって、安易な事実認定につながるわけではないことは注意が必要です。
須藤氏は、民事訴訟における証明度を考えるにあたって、刑事訴訟との違いを明快に論じています。
第1に、刑事訴訟では権力濫用の歴史を踏まえて積極的誤判を避けるため、高度の蓋然性を用いて消極的誤判には目をつぶることはやむを得ないといえるものの、民事訴訟では基本的に対等な当事者間の争いであり、安易にやむを得ないとして切り捨てることは誤りとします。
第2に、民事訴訟では平等な当事者をできるだけ公平に扱うことが必要であるから、事実認定においても、当事者双方の平等をできるだけ重視した証明度を原則とすべきところ、高度の蓋然性では一方当事者にだけ極めて高い証明責任を貸す不平等なもの、と批判します。
第3に、元々は刑事訴訟で用いられた「高度の蓋然性」という用語を民事訴訟でも用いることで、裁判官による事実認定に弊害が生じるとします。すなわち、刑事訴訟を担当した裁判官が民事訴訟を担当することもあり、「高度の蓋然性」という用語について刑事訴訟における極めて厳格な証明度に影響されて、民事事件では証明の程度が低すぎて全て請求棄却ということになりやすくなってしまいます。高度の蓋然性の呪縛によって、当事者も裁判所もより確実な証拠の獲得を目指して精密司法のジレンマに陥り、審理の長期化、適正かつ迅速な民事訴訟の実現が妨げられるという大きな弊害が生じているといいます。
医療訴訟については、東京地裁や大阪地裁等、複数の地域の地方裁判所で医療集中部が設けられており、そこでは医療事件が主に扱われています。医療集中部に所属している裁判官は総じて非常に勉強熱心で、当該訴訟で問題となっている医療について深く理解しようとする姿勢を強く感じます。当事者双方から提出される医学文献は大量かつ専門性の高いものになり、また非常に高度な議論が行われることも多く、その意味では精密司法が実践されているといえるでしょう。
しかし、証明度の基準として「高度の蓋然性」が用いられる以上、どれだけ精緻な主張立証がされても、高度の蓋然性までは認められないということで、請求棄却(あるいはせいぜい相当程度の可能性として低額な慰謝料)になるという経験を多くの患者側弁護士は有しているはずです。精密司法の名のもと、高度の蓋然性という極めて高いハードルを設けられることで、患者側はスタート時点から不利な立場に立たされていることになります。まさに須藤氏がいう精密司法のジレンマです。
高度の蓋然性の壁を打ち破るための方策はこれまでも述べられてきましたが、裁判実務は変わっておらず、患者不利の状況は続いています。
ただ、以前のブログで紹介したように、「相当程度の可能性」しか認められない場合でもその可能性の程度に応じて逸失利益を認めるべきとする論稿が元裁判官の杉原則彦氏から出されました。
https://osakairyo-ken.net/blog/catgory01/405/
これに加えて、今回の須藤氏の論稿も出されました。以前からもその動きはありましたが、最近になって医療訴訟における立証の不平等を改善する論稿が目立つ印象です。
患者側としては、杉原論文に加えて、今回の須藤論文も提出して、硬直化した「高度の蓋然性」という呪縛から裁判所と当事者を解き放ち、双方の主張と証拠を柔軟かつ合理的に評価することで、よりバランスの取れた公正な事実認定につながるよう働きかけていくことが重要になるでしょう。
会員弁護士 Y.U