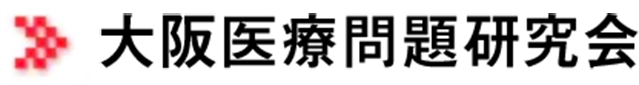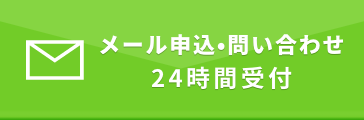研修会『医師模擬尋問』を受講しました
2025.03.25
2025年3月8日、名古屋市内で行われた研修会「医師模擬尋問」に参加しました。
この研修会は、南山大学法曹実務教育研究センター、愛知県の医療過誤問題研究会、医療事故情報センターの共催により開催され、受講者は、同センター会員及び各地の弁護団・研究会所属の弁護士、南山大学法科大学院生でした。
医療過誤事件に精通した弁護士が、裁判官役(裁判長と右陪席は元裁判官)、原告代理人役、被告代理人役を務め、被告医療機関側の証人(現役医師)に対して証人尋問を行うというものです。
当研究会からは、H弁護士が被告代理人弁護士役を務めたほか、医師でもあるA弁護士がコメンテーターとして参加しました。
研修といえども、実際の法廷と同様の法科大学院の法廷教室を使用し、参加者は傍聴席の位置から観るので、本物の裁判所同様の臨場感があり、また、尋問内容につき双方代理人の間で事前の打ち合わせがなされていないため、双方の代理人は、その場で臨機応変な対応が要求されるなど、実際の証人尋問のような緊張感がありました。
事案は、意識レベルの低下が認められた高齢の患者が被告病院の救急外来を受診した際、一過性の意識障害の悪化と診断されて帰宅を指示されたものの、翌日別の病院に救急搬送され実施された頭部MRI検査の結果、血栓性脳梗塞と診断され、その後歩行不能のため常時介護が必要な状態となったというものでした。
主な争点は、被告病院を受診した時点で、一過性脳虚血発作(TIA 一時的に脳の血管が詰まることにより、脳梗塞になる一歩手前の状態)の発症を疑い、必要な措置をとるべきであったといえるかです。
被告側は、主尋問において、診察時に脳の局所的な血流不全を示す片麻痺などのTIAを疑う症状がなく、CT画像で脳梗塞像を認めないことなどから、救急外来の対応としては問題がなかったことを示す事情を淡々と確認していきました。
原告側は、反対尋問において、下肢脱力や下肢MMT低下などのカルテ上の記載を指摘したり、TIAの重症度を示すABCDスコアによる評価などについて質問しました。
裁判官による補充尋問を経て尋問手続が終了し、直後に行われた傍聴人の挙手によるジャッジでは、なんと全員が被告病院に過失なしとの意見でした。
後で被告代理人役のH弁護士に聞いたところによれば、医師証人が非常に熱心に記録を読み込み、入念な反対尋問対策を行ったということでしたので、反対尋問で医師証人の主尋問を崩すことが容易ではないことを実感しました。
最後に、参加者全員による講評・意見交換が行われました。「原告側尋問では、獲得目標を明確にし、文献を示すなどして裁判官がイメージを持ちやすいように工夫する」、「カルテを詳細に検討して医師の主張に反する箇所を指摘する」、「反対尋問で不利益事実を認めさせる」、「脳梗塞の発生と発症は別であり、画像の分析・評価が重要」、「血液検査結果などの経時的な変化に注目する」など、経験豊富な弁護士の意見やノウハウに加え、証人役やA弁護士ら現役医師の意見や感想はとても参考になりました。
当研究会に所属する弁護士は、会内の例会や勉強会のほか、今回ご紹介したような他団体が主催する研修へも参加し、全国の患者側弁護士との交流や情報交換を通じて、医療過誤訴訟の研鑽に努めています。
会員弁護士 S.D